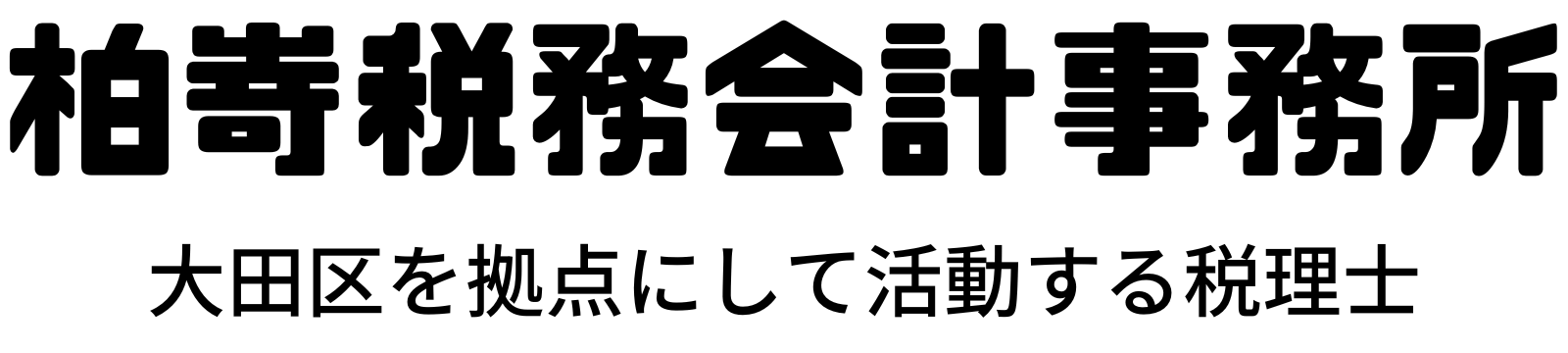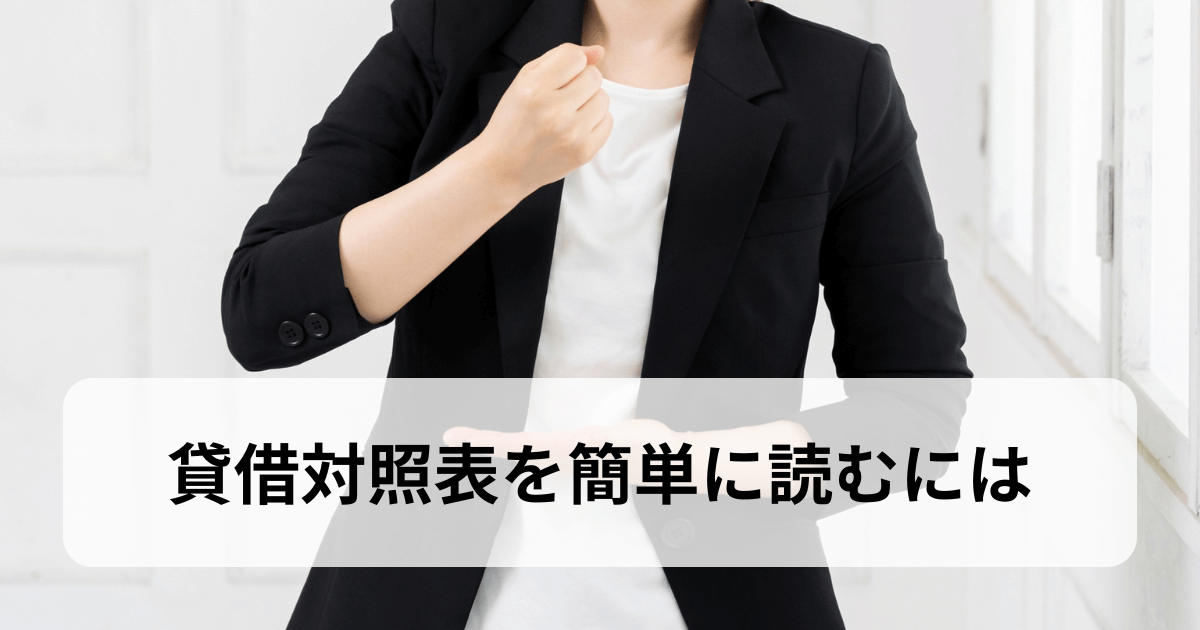貸借対照表は、難しいです。
損益計算書よりも、かなり難しいですね。
貸借対照表は、負債と純資産がお金の調達方法です。
そして、資産はお金の使い道となります。
貸借対照表は、2期並べて読むと、ながれがわかります。
この記事を読んで、貸借対照表の読み方を確認しましょう。
貸借対照表の読み方
貸借対照表は、資産、負債と純資産に別れています。
どこから見るのかというと、負債と純資産から見ます。
その理由は、負債と純資産は、お金の調達方法だからです。
負債がお多ければ、他人からの調達が多いことになります。
純資産が多ければ、資本金や過去の利益の集まりからお金を調達しているということです。
まずは、負債と純資産から確認してみましょう。
たぶん、気になるのは負債の項目で、借入金以外だと思います。
借入金以外で、お金を調達しているってなんなの?と思うでしょう。
でも、借入金以外でも、お金を調達しています。
例えば、買掛金です。
買掛金というのは、材料などを仕入れたんだけど、後払いするときに出てくる勘定科目です。
本当は、材料を買ったときに、お金は出ていきます。
でも、後払いなので、お金がでていきません。
材料はあるけどお金の支払いがないということは、お金を調達したのと同じ事なのです。
買掛金は、将来払うお金という見方もありますが、貸借対照表を作ったときは、お金を払っていないので、お金を調達したとなるのです。
預り金なども、同じような感じです。
預り金は、社員から預かった税金などを表します。
お金を預かるということは、お金を調達したということになるのです。
貸借対照表を見るときは、まずは負債と純資産の部を確認しましょう。
貸借対照表の資産の部の見方
貸借対照表の資産の部は、お金とお金の使い道が書いてあります。
負債と純資産で調達したお金が、なにになっているのか?ということですね。
お金のままであればいいのですが、そんなことはないですよね。
会社を運営するには、お金を使う必要があります。
売掛金などは、将来お金になるという勘定科目です。
商品などは、お金を使って仕入れた商品ですね。
車両や建物なんかも、お金を使った購入したものとなります。
つまり、貸借対照表は、お金とお金の使い道が書いてあります。
貸借対照表は、どんなふうにお金を使って来たのかが、わかるのです。
貸借対照表は、2つ並べて理解しよう
貸借対照表は、作ったものだけをみると、数字が書いてあるだけなので、あまり理解できません。
貸借対照表は、作った時点での財政状況を表しているからです。
貸借対照表は、2つ並べて確認するほうが理解ができます。
その理由は、流れがわかるからです。
たとえば、前期と今期の貸借対照表を並べて、数字の違うところを確認します。
多くなったり少なくなったりするところを確認することにより、お金をどうやって調達して、どんなふうに使ったのかがわかるのです。
貸借対照表の今期だけをみても、実感はでてきません。
貸借対照表は、2期分を並べて理解しましょう。
貸借対照表の簡単な読み方を考えてみるのまとめ
貸借対照表は、難しいです。
読めるようになると、お金の流れがわかります。
ぜひ、チャレンジしてみましょう。
編集後記(2154)
髪を切ったのですが、この時期は、髪を切ると風邪を引きやすいので、首にタオルを巻いています。
髪を切ったときは、これが1番風邪予防には効きます。
55日記(2484)
「今日は楽しかった」と保育園のことを、しゃべってくれました。
お友達から、ピアノ教室のことも聞いてきたみたいです。
66日記(1711)
テレビで見た、みかんのかんづめを食べました。
なんかじっくり食べているのですが、いっぱいあるので、早めに食べてほしい。