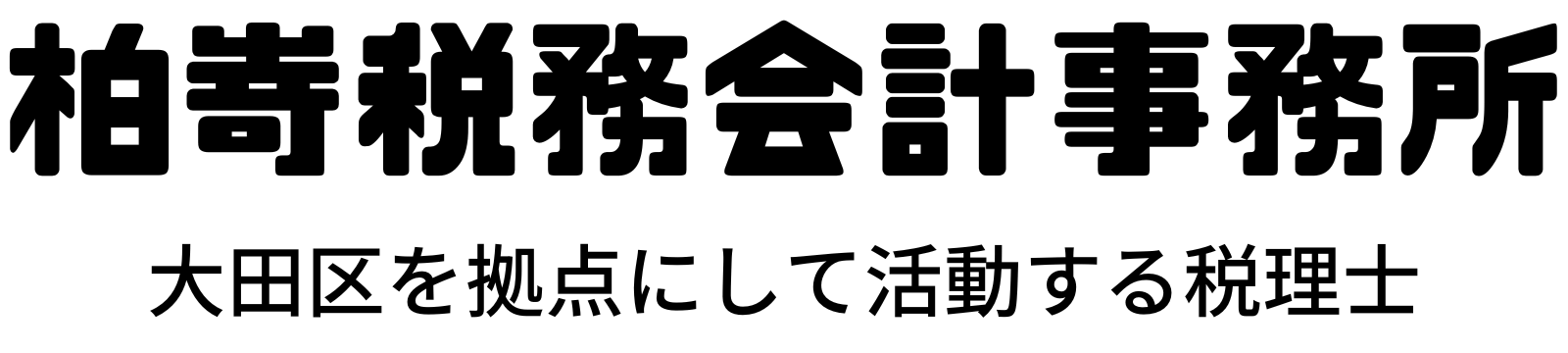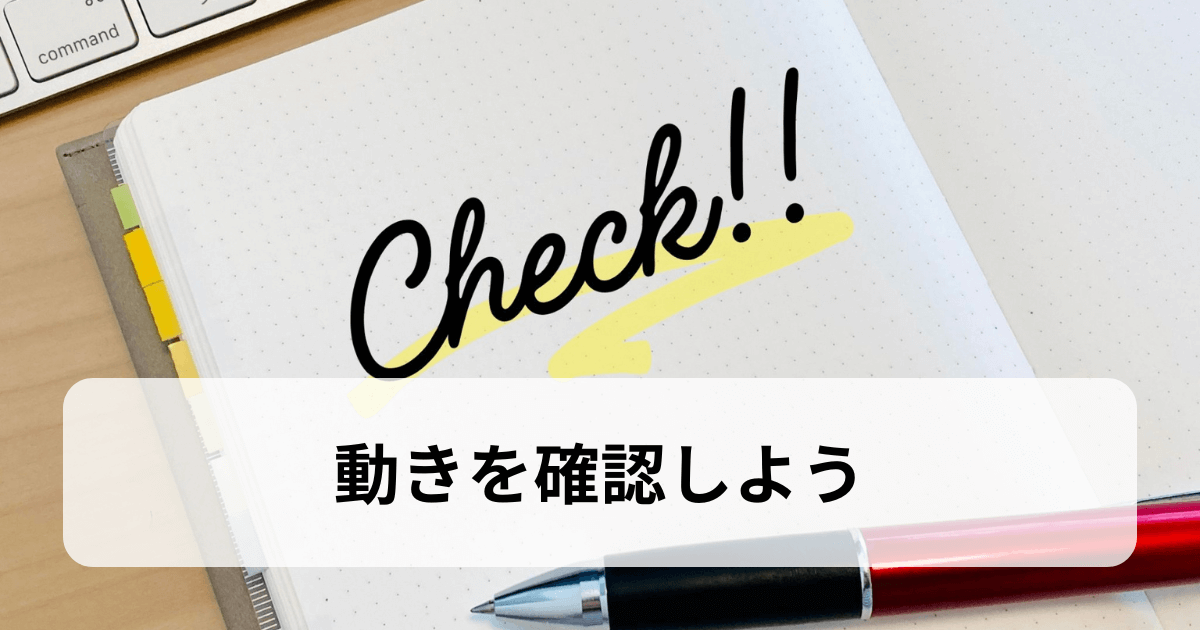貸借対照表が読めないと悩んでいませんか?
貸借対照表は、数字をみただけでは、わかりません。
なにが起きたらどうやって動くのか?を確認しないと、理解できないです。
この記事を読んで、貸借対照表の動きを確認しましょう。
貸借対照表を読めないのは、動きを知らないだけです。
貸借対照表って読めますか?
なんとなく、わかりにくいですよね。
貸借対照表は、お金や商品などを動かすことにより、動いているのです。
そのため、貸借対照表の動きを確認していないと、貸借対照表は読めません。
貸借対照表の動きを確認していきます。
貸借対照表の基本としては、
・損益計算書の利益と貸借対照表の純資産はつながっている
・取引によっては、損益計算書が動かないことがある
・取引によっては、現金が動く場合と動かない場合がある
では、貸借対照表の動きについて、確認してきます。
貸借対照表の動き
500円の売上があり、現金500円をもらった
500円の売上があり、現金500円もらったなんですけど、仕訳としては次のようになります。
| (借方) | (貸方) |
| (現金)500 | (売上)500 |
仕訳をみてもらうとわかるのですが、現金は、貸借対照表に書いてある項目であり、売上は貸借対照表には書いていません。
でも、貸借対照表はバランスシートと言われていますので、現金が増えてたら、どこかが増えなきゃいけないのです。
どこが増えるのかというと、純資産が増えます。
売上が500というのとは、利益が500になるので、現金(資産)が500増えて、純資産が500増えます。
損益計算書の利益と貸借対照表の純資産がつながっているというのは、こういう意味となります。
売掛金500円を現金で集金した
販売してもらっていなかった代金の500円を現金で回収したのですが、仕訳は次のようになります。
| (借方) | (貸方) |
| (現金)500 | (売掛金)500 |
仕訳をみると、現金と売掛金しか出て来ません。
現金と売掛金は、両方資産で表す勘定科目となります。
貸借対照表は、バランスシートですから、バランスを取らなければいけないのですが、現金(資産)が増えて、売掛金(資産)が500減っています。
資産が、同じ金額増えて減っているので、バランスは変わりません。
この取引は、貸借対照表の勘定科目のみが動いているため、損益計算書は動かないということです。
商品を500円で仕入れて、現金500円を払った
商品を現金500円で仕入れて、現金500円を払ったのですが、仕訳は次のようになります。
| (借方) | (貸方) |
| (仕入)500 | (現金)500 |
仕訳を見ると、貸借対照表にでてくる勘定科目は、現金だけです。
現金が500減っているので、バランスを取るためには、純資産を500減らす必要があります。
損益計算書にでてくる勘定科目と貸借対照表に出てくる勘定科目の仕訳の場合は、損益計算書に出てくる勘定科目は、貸借対照表の純資産で増減させます。
純資産が、損益計算書の利益とつながっているのです。
商品を500円を掛けで売った
商品500円を掛けで売った場合ですが、仕訳は次のようになります。
| (借方) | (貸方) |
| (売掛金)500 | (売上)500 |
この仕訳は、売掛金が増えて、売上が増えるのです。
貸借対照表では、資産が増えて、純資産が増えます。
今回の仕訳は、現金は絡んでこないので、現金の増減はありません。
貸借対照表の動きは、貸借対照表のどこかが増えたら、どこかが増えたり減ったりすることの集まりとなります。
貸借対照表の動きというのは、いったいなんだ?
貸借対照表のうごきというのは、貸借対照表に書いてある勘定科目の動きとなります。
それ以外の損益計算書に書いてある勘定科目は、純資産で処理されるということです。
貸借対照表の動きは、勘定科目でなにが動いているかがわからないと、わかりにくいのです。
ただ数字をみているだけでもわかりませんし、その時点だけみていても動きはわかりません。
例えば、前期の貸借対照表と比較して、現金が増えていたとします。
現金が増えていたら、他はどうなってるんだろう?と探す必要があります。
仕訳は、必ず2つの勘定科目が使われます。
| (借方) | (貸方) |
| (現金) | ? |
この?の部分になにが入るのかを確認することが、貸借対照表の動きを確認することになります。
?に入ってくる勘定科目は、
・資産勘定
・負債勘定
・損益計算書に出てくる勘定
となります。
資産勘定は、
| (借方) | (貸方) |
| (現金) | (売掛金) |
とかですね。
負債勘定は、
| (借方) | (貸方) |
| (現金) | (借入金) |
とかになります。
そして、損益計算書に出てくる勘定科目は
| (借方) | (貸方) |
| (現金) | (売上) |
などになります。
パターンとしては、この3つしかありません。
そのため、貸借対照表の動きというのは、限定されているのです。
数字だけをみていると、なんだかわからないのは、うごきを確認していないからです。
この動きを理解して貸借対照表をみると、貸借対照表がわかってきます。
貸借対照表は、負債と純資産が、お金の調達方法を表していて、資産がお金とお金の使い道が書いてあります。
貸借対照表を前期と比較して、負債が増えていれば、考えられることは3つです。
・資産が増えている
・負債が減っている
・純資産が減っている
のどれかとなるのです。
そして、それを探していくように読んでいくと、貸借対照表がわかる様になってきます。
初めは慣れないかもしれませんが、意識して読むとわかるようになっていきます。
貸借対照表の理解には、簿記は必要なのか?
よくある話で、社長は簿記がわかっていないといけないのか?なんですけど、貸借対照表を理解するには必要です。
その理由は、貸借対照表に出てくる勘定科目が理解できないと、動きもわからないからです。
勘定科目と基本的な動きが理解できれば、貸借対照表は読めるようになるでしょう。
・・・なるでしょうというのは、貸借対照表は、奥が深いです。
税理士の私でも、全部理解しているのかと聞かれると、なかなか答えに苦しみます。
そのため、お金の動きに絞って確認する、図解する、比較する、などをやってみましょう。
ただ数字だけみていても、得られる情報は少ないです。
貸借対照表を読めないのは、動きを知らないだけですのまとめ
貸借対照表を理解するというのは、かなり大変なテーマだと思います。
動きを確認して、理解するのが良いので、簿記を学ぶというのも必要でしょう。
編集後記(2257)
Alexaとアップルミュージックを連携させようと思ったのですが、できませんでした。
なんか難しいので、諦めます。
55日記(2587)
水筒のフタが閉まっていなくて、おじぎをしたら、ランドセルの横からお茶が出てきました。
紙は、ほとんどが濡れていました。
66日記(1814)
手に豆ができていますが、公園に行くと毎回うんていをしています。
今度は、鉄棒の逆上がりを、できるようにするそうです。